



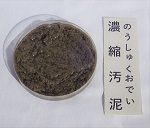



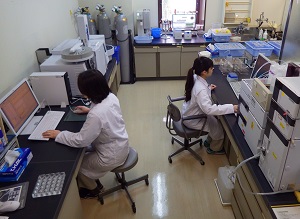

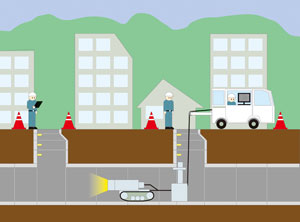
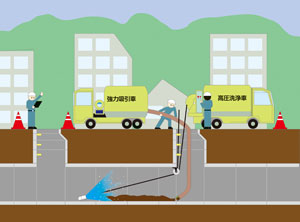

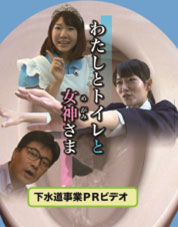
城北水質管理センターでは、施設見学(完全予約制)を受け付けています。
印刷用pdfはこちらです。 |
|||
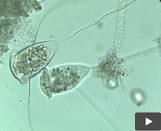 ①ボルティセラ(Vorticella)別名:ツリガネムシ頂部の繊毛(せんもう)で水流を起こしながら、遊泳する細菌類を捕食する。
①ボルティセラ(Vorticella)別名:ツリガネムシ頂部の繊毛(せんもう)で水流を起こしながら、遊泳する細菌類を捕食する。
|
 ②エピスティリス(Epistylis)ボルティセラとよく似ており、群体をなす。柄に糸状の筋はみられない。
②エピスティリス(Epistylis)ボルティセラとよく似ており、群体をなす。柄に糸状の筋はみられない。
|
 ③オペルクラリア(Opercularia)ボルティセラ、エピスティリスに類似している。柄は分岐し群体を作る。柄に糸状の筋がある。
③オペルクラリア(Opercularia)ボルティセラ、エピスティリスに類似している。柄は分岐し群体を作る。柄に糸状の筋がある。
|
 ④トコフィリア(Tokophrya)先端の2か所または4か所から吸管を出し、近づいてきた原生動物を吸管で捉えて体液を吸収する。
④トコフィリア(Tokophrya)先端の2か所または4か所から吸管を出し、近づいてきた原生動物を吸管で捉えて体液を吸収する。
|
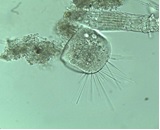 ⑤アキネタ(Acineta)トコフィリアとよく似ており、太くて短い柄を出しフロックに付着している。
⑤アキネタ(Acineta)トコフィリアとよく似ており、太くて短い柄を出しフロックに付着している。
|
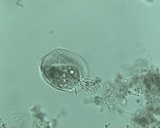 ⑥アスピディスカ(Aspidisca)別名:メンガタミズケムシフロックの周りをテクテクと動き回っている。
⑥アスピディスカ(Aspidisca)別名:メンガタミズケムシフロックの周りをテクテクと動き回っている。
|
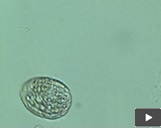 ⑦プロロドン(Prorodon)別名:タマミズケムシ体全体に生えた繊毛(せんもう)を使いくるくると回転しながら遊泳する。
⑦プロロドン(Prorodon)別名:タマミズケムシ体全体に生えた繊毛(せんもう)を使いくるくると回転しながら遊泳する。
|
 ⑧リトノータス(Litonotus)前後に滑るように移動する。口がある細長いほうを前にして遊泳する。
⑧リトノータス(Litonotus)前後に滑るように移動する。口がある細長いほうを前にして遊泳する。
|
 ⑨アンフィレプタス(Amphileptus)リトノータスに似ているが、やや大型でゆっくり動く。
⑨アンフィレプタス(Amphileptus)リトノータスに似ているが、やや大型でゆっくり動く。
|
 ⑩ペラネマ(Peranema)二つの鞭毛(べんもう)があり、直進時は鞭毛(べんもう)を前方に伸ばして滑るように移動する。方向転換時は体を丸めて静止する。
⑩ペラネマ(Peranema)二つの鞭毛(べんもう)があり、直進時は鞭毛(べんもう)を前方に伸ばして滑るように移動する。方向転換時は体を丸めて静止する。
|
 ⑪アルセラ(Arcella)別名:ナベカムリ殻は円筒形。若い細胞は透明に近く、老化するにつれ濃褐色を示す。
⑪アルセラ(Arcella)別名:ナベカムリ殻は円筒形。若い細胞は透明に近く、老化するにつれ濃褐色を示す。
|
 ⑫ユープロテス(Euplotes)フロックの周りを動き回っている。アスピディスカより大型で足の数も多い。
⑫ユープロテス(Euplotes)フロックの周りを動き回っている。アスピディスカより大型で足の数も多い。
|
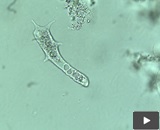 ⑬アメーバ(Amoeba)体は扁平で一定の形を持たず、仮足を出して形を変えながら移動する。
⑬アメーバ(Amoeba)体は扁平で一定の形を持たず、仮足を出して形を変えながら移動する。
|
 ⑭ブレファリズマ(Blepharisma)下水処理場でみられる微生物の中で、珍しくピンク色をしている。あまり形をを変えずにゆっくりと遊泳する。
⑭ブレファリズマ(Blepharisma)下水処理場でみられる微生物の中で、珍しくピンク色をしている。あまり形をを変えずにゆっくりと遊泳する。
|
 ⑮スピロストマム(Spirostomum)別名:ネジレクチミズケムシ大型で細長い形をしていて、水中を滑るように移動する。
⑮スピロストマム(Spirostomum)別名:ネジレクチミズケムシ大型で細長い形をしていて、水中を滑るように移動する。
|
 ⑯カエトノツス(Chaetonotus)別名:イタチムシ体全体に繊毛(せんもう)が生じていて、尾部は二股に分かれる。移動は速い。
⑯カエトノツス(Chaetonotus)別名:イタチムシ体全体に繊毛(せんもう)が生じていて、尾部は二股に分かれる。移動は速い。
|
 ⑰ロタリア(Rotaria)別名:ヒルガタワムシ昼ヒルのように伸び縮みしながら移動する。頭部の繊毛(せんもう)を動かして、小型の細菌類を捕食する。
⑰ロタリア(Rotaria)別名:ヒルガタワムシ昼ヒルのように伸び縮みしながら移動する。頭部の繊毛(せんもう)を動かして、小型の細菌類を捕食する。
|
 ⑱レパデラ(Lepadella)別名:ウサギワムシ尾部が二つに分かれており、ウサギの耳のように見える。水中をすばやく遊泳する。
⑱レパデラ(Lepadella)別名:ウサギワムシ尾部が二つに分かれており、ウサギの耳のように見える。水中をすばやく遊泳する。
|
 ⑲ネマトーダ(Nematoda)体をくねくねさせながらフロックの中に潜り込んで、細菌類を捕食する。
⑲ネマトーダ(Nematoda)体をくねくねさせながらフロックの中に潜り込んで、細菌類を捕食する。
|
 ⑳ズーグレア(Zoogloea)樹状、雲状のコロニーを形成する。凝集性のある分泌物質をだし、活性汚泥法では欠かせない存在。
⑳ズーグレア(Zoogloea)樹状、雲状のコロニーを形成する。凝集性のある分泌物質をだし、活性汚泥法では欠かせない存在。
|